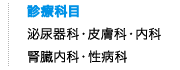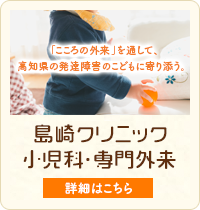■~梅毒について~
こんにちは!高知市の島崎クリニックの院長島崎です。
「最近ニュースで梅毒の流行をよく聞くけれど、自分の症状と関係あるのだろうか?」「梅毒の検査はどこで受けられるのだろうか?」といった不安や疑問を感じて、このページを開いてくださったことと思います。性感染症は非常にデリケートな問題であり、誰にも相談できずに悩んでいる方が多いことを、泌尿器科医として日々感じています。
この記事では、近年報告数が急増している梅毒について、その基本的な知識から、症状の進行段階、現代の日本における流行状況、そして高知市の地域医療として当院が提供する検査・治療法、さらには効果的な予防策までを、詳しくかつ分かりやすく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、梅毒についての正しい知識が身につき、不必要な不安を解消し、早期発見・早期治療に向けた具体的な行動を起こすきっかけを得ることができます。
この記事は、身体の異変に気づき不安を感じている方、性感染症の感染リスクに心当たりのある方、そして梅毒でお困りのご家族はぜひ最後まで読んでみてください!
梅毒について知る:なぜ今、日本で急増しているのか
梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌によって引き起こされる性感染症(STI)です。過去の病気というイメージを持つ方もいますが、現在、日本全国で報告数が急増しており、特に注意が必要な状況です。
日本における梅毒の深刻な流行状況
梅毒の感染者報告数は、近年、増加傾向にあります。厚生労働省のデータによると、2014年には年間約1,700件だった報告数が、2022年には10,000件を超え、2024年の報告数(暫定値)は1万4,663人と、感染症法上の届出を開始して以降、最多となった2023年の報告数をわずかに下回ったものの、依然として高い水準で推移しています。
この流行の特徴として、特に20代の女性の感染報告数が突出して多い一方で、男性は20代から50代まで幅広い層で報告されています。この急速な増加は、梅毒についての正しい知識と早期検査の重要性を改めて示しています。
梅毒の主な感染経路と潜伏期間
梅毒は、主に性的な接触によって感染します。具体的には、感染者の皮膚や粘膜にできた病変部と、非感染者の粘膜や小さな傷口が直接接触することで、病原体が体内に侵入します。
-
感染経路の具体例:膣性交だけでなく、オーラルセックス(口腔性交)やアナルセックス(肛門性交)によっても感染します。キスだけでも感染する可能性が指摘されています。
-
潜伏期間:梅毒トレポネーマが体内に侵入してから、最初の症状が現れるまでの潜伏期間は、通常3週間から3か月程度です。この潜伏期間中は症状がないため、感染に気づかないままパートナーに感染させてしまうリスクがあります。
梅毒の進行と見逃せない症状の段階
梅毒は、治療せずに放置すると、時間の経過とともに症状が変化しながら進行していくのが特徴です。その症状は、感染から経過した期間によって第1期、第2期、第3期、第4期、そして無症状の潜伏梅毒に分類されます。
感染初期:第1期梅毒の症状(感染後約3週間~3か月)
梅毒に感染してから約3週間〜3か月の間に現れるのが第1期梅毒です。この時期の症状は、感染が起きた部位(性器、肛門、口唇など)に、初期硬結と呼ばれるしこりや、それが破れてできる**硬性下疳(かい)という潰瘍(かいよう)**が現れることです。
-
症状の特徴:これらの病変は、通常痛みがないことが多く、「大したことない」と見過ごされがちです。
-
リンパ節の腫れ:太もものつけ根(鼠径部)のリンパ節が腫れることもありますが、これも痛みがないことが多いため、見逃しやすいです。
この第1期の症状は、治療をしなくても数週間で自然に消えてしまいます。しかし、症状が消えたからといって治ったわけではなく、体内で梅毒が進行している潜伏梅毒の状態に移行します。私は過去に、小さなできものが自然に消えたため完治したと思い込み、数カ月後に全身に発疹が出て驚いて来院された患者様を診察したことがあります。症状が消えても、必ず検査と治療を継続することが重要です。
感染中期:第2期梅毒の症状(感染後数ヶ月~数年)
第1期症状が消失した後、数週間から数カ月後に、病原菌が血液に乗って全身に広がり、第2期梅毒の症状が現れます。この時期は最も梅毒の感染力が強い時期です。
-
梅毒性バラ疹:手のひら、足の裏、体幹など全身に、赤っぽい小さな発疹(梅毒性バラ疹)が現れます。この発疹も痛みやかゆみがほとんどないため、風疹やアレルギーと間違われることがあります。
-
その他の症状:脱毛、扁桃腺の腫れ、発熱、倦怠感などが現れることもあります。
-
粘膜病変:口の中やのど、性器の粘膜に扁平コンジローマと呼ばれる白っぽいできものができることもあります。
この第2期の症状も、治療しなくても数週間から数カ月で自然に消えたり、軽くなったりすることがありますが、その後も再発を繰り返す可能性があります。症状が消えたからと自己判断で治療を中断すると、早期神経梅毒など脳神経関連の重い症状を引き起こす恐れもあります。
進行期:第3期以降の梅毒(感染後数年~数十年間)
第2期の後、治療をせずに放置すると、数年~数十年という長い潜伏期間を経て、第3期、第4期へと進行し、心臓、血管、脳、神経など、体のさまざまな臓器に重い障害を引き起こします。
-
第3期梅毒:皮膚や骨、筋肉などにゴムのような塊(ゴム腫)ができ、進行すると臓器の機能が不可逆的に破壊され、後遺症が発生する可能性が高くなります。
-
第4期梅毒:大動脈瘤などの心血管梅毒や、神経梅毒(麻痺、認知機能の障害など)を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。
梅毒は、一度感染すると体内に抗体が残るため、完治後も抗体検査(TPHA法など)は陽性のままとなります。しかし、適切な治療を受ければ早期の段階で完治が可能な病気です。
梅毒の検査・診断と完治を目指す治療法
梅毒の早期治療は、重症化を防ぎ、他者への感染拡大を防ぐために極めて重要です。疑わしい症状や心当たりのある方は、ためらわずに検査を受けることが必要です。
泌尿器科で行う梅毒の検査方法
梅毒の診断は、主に血液検査で行います。高知市の島崎クリニックでは、採血による以下の2種類の抗体検査(RPR法とTPHA法またはFTA-ABS法などのTP抗体検査)を組み合わせて行います。
-
RPR法(STS法):治療によって数値が変動するリン脂質抗体の量を測定します。この数値が治療効果を判断する際の重要な指標となります。
-
TPHA法など:梅毒トレポネーマに対する抗体を測定します。一度感染すると完治後も陽性が続くことが多い検査です。
検査費用は、自由診療の場合、医療機関によって異なりますが、血液検査で7,000円〜9,000円程度が相場です。保険診療の場合は、初診料を含めて約1,700円〜2,000円程度(3割負担の場合)で検査を受けられる場合が多く、当院でも保険診療での検査が可能です。感染の機会から4週間以降に検査を受けることで、より正確な結果が得られます。
梅毒の完治を目指す治療の選択肢とその注意点
梅毒の治療は、主に抗菌薬(ペニシリン系)の服用または注射によって行います。病気の進行度(期数)に応じて、治療期間が異なります。
1. 経口抗菌薬(内服治療)の具体的な治療期間
梅毒の内服治療は、病期によって治療期間が異なります。
-
第1期梅毒:通常2週間から4週間の抗菌薬の内服治療を行います。
-
第2期梅毒:通常4週間から8週間の抗菌薬の内服治療を行います。
メリット
-
内服治療であるため、比較的患者様の身体的負担が少ないです。
-
治療期間の目安がガイドラインによって明確に定められています。
-
自宅で服用できるため、通院回数を抑えられる場合があります。
-
他の性感染症の治療薬も同時に内服できる場合があります。
デメリット
-
梅毒の完治には、医師の指示通りに薬を飲み続けることが不可欠です。症状が消えたからと自己判断で服用を中断すると、再発のリスクが非常に高まります。
-
薬の副作用(アレルギー反応など)が出る可能性があるため、服用中は注意が必要です。
-
内服治療中は、最低でも半年間は性行為を控え、治療に専念する必要があります。
-
内服治療終了後も、さらに1年間は定期的な血液検査で再発の有無をチェックする必要があります。
2. 注射薬による治療のメリットと可能性
日本では、梅毒の治療薬として、1回の注射で効果が持続するベンジルペニシリンベンザチン(商品名:ベンザシリン)という筋肉注射が導入されています。
メリット
-
早期梅毒(第1期、第2期、早期潜伏梅毒)であれば、原則1回の筋肉注射で治療が完了する可能性があります。
-
内服薬のように、毎日飲み続ける必要がないため、飲み忘れの心配がなく、治療を確実に進められるという大きな利点があります。
-
治療を確実に完了できるため、薬の自己中断による再発リスクを大幅に減らせます。
-
海外では標準的な治療法であり、高い有効性が確認されています。
デメリット
-
注射の際の痛みが伴うことがあります。
-
ペニシリンアレルギーのある方はこの注射を受けることができません。
-
進行した梅毒(後期潜伏梅毒、神経梅毒など)の場合、内服や点滴による治療が必要になることがあります。
-
注射後も、治療効果を確認するために定期的な血液検査(半年~1年)は必要です。
梅毒の再感染と予防のために:大切な人を守る行動
梅毒は一度完治しても、再び感染(再感染)する可能性がゼロではありません。あなた自身と大切なパートナーを守るために、継続的な予防と検査が重要です。
梅毒の感染拡大を防ぐための具体的な予防策
梅毒の感染を予防するための基本は、安全な性行動を心がけることです。
-
コンドームの正しい使用:性行為の際には、コンドームを最初から最後まで適切に使用しましょう。コンドームは梅毒の感染リスクを減らしますが、コンドームが覆わない皮膚や粘膜の病変部から感染する可能性もあるため、100%予防できると過信しないことが重要です。
-
オーラルセックス・アナルセックスへの注意:膣性交だけでなく、オーラルセックスやアナルセックスでも梅毒は感染します。これらの行為の際も、必ずコンドームを使い、粘膜の直接接触を避けてください。
-
不特定多数との性的接触を避ける:多数のパートナーとの性的接触は、梅毒の感染リスクを大幅に高めます。
-
定期的な検査:感染の機会があった方や、複数のパートナーがいる方は、無症状であっても定期的な検査を受けることで、早期発見・早期治療につなげることができます。
パートナーと自分を守るための行動
梅毒と診断された場合、パートナーも感染している可能性が極めて高いため、パートナーにも速やかに検査と治療を勧めることが重要です。また、治療によって症状が消えたとしても、医師が「完治」と判断するまでは、性行為を控えることが、梅毒の感染拡大を防ぐ上で最も重要です。
まとめ
梅毒についての正しい知識は、あなた自身と大切な人を守るための最初の一歩です。梅毒は現在、日本全国で急増しており、特に高知市にお住まいの皆さまにも、決して他人事ではない病気であるという認識を持っていただくことが大切です。
梅毒は、感染から時間が経つにつれて症状が変化し、放置すると重篤な後遺症を残す可能性のある病気ですが、早期に発見し、適切な抗菌薬治療(内服または注射)を行えば完治が可能な病気です。症状がなくても、感染の心当たりがある方は、ぜひ梅毒の検査を受けてください。
本記事をお読みいただきありがとうございます。何かご不明な点や、お悩みがございましたら、高知市の島崎クリニックにお気軽にご相談ください。